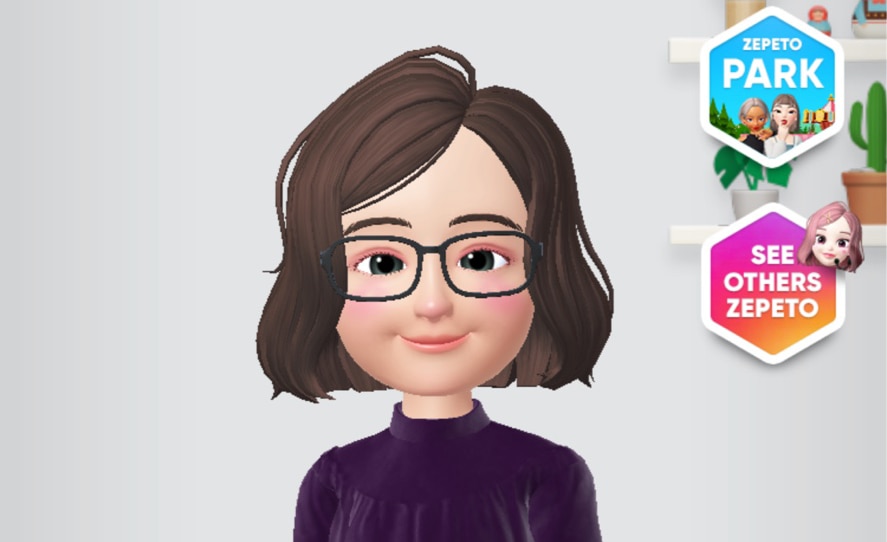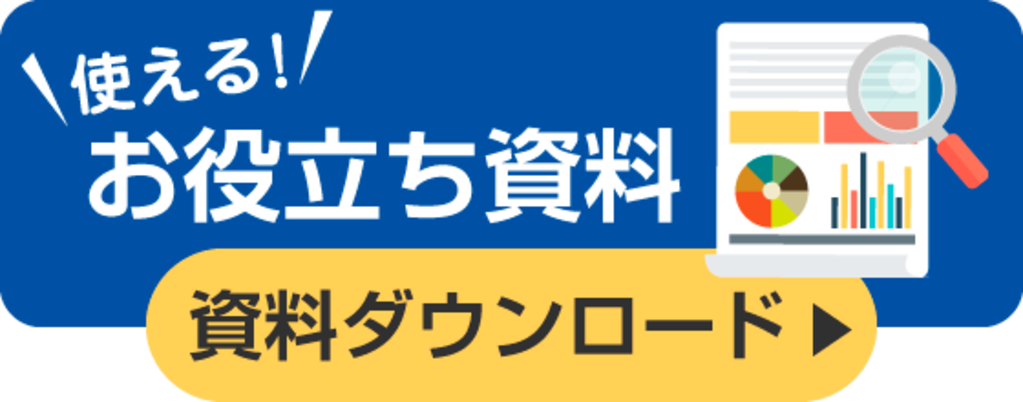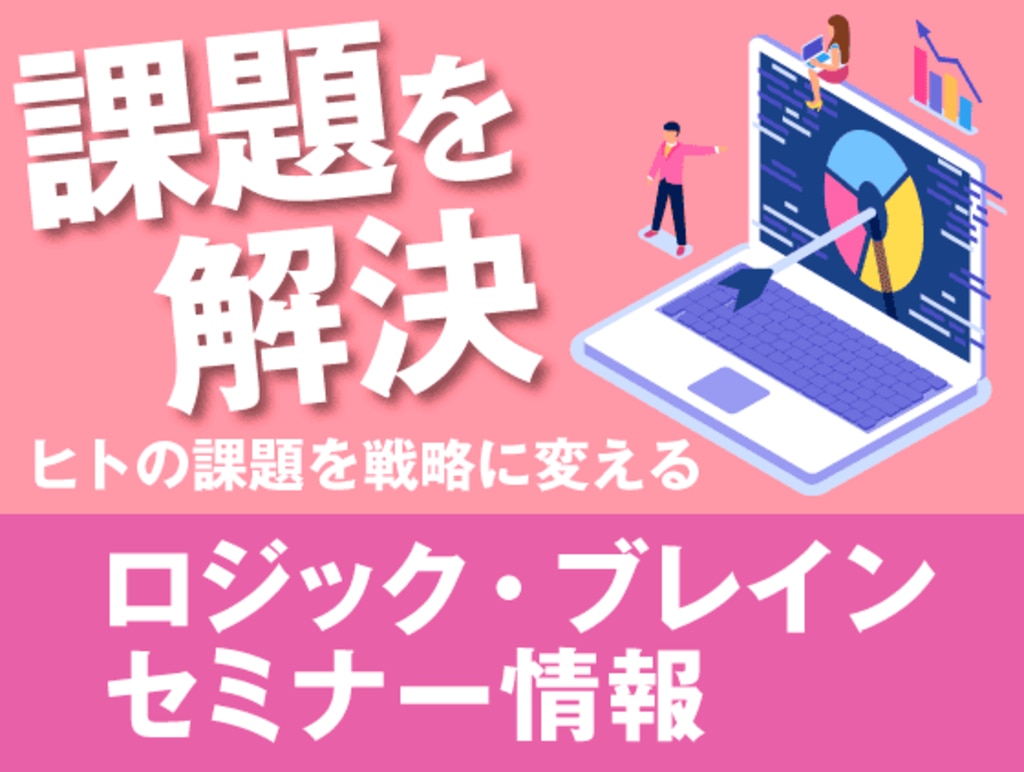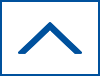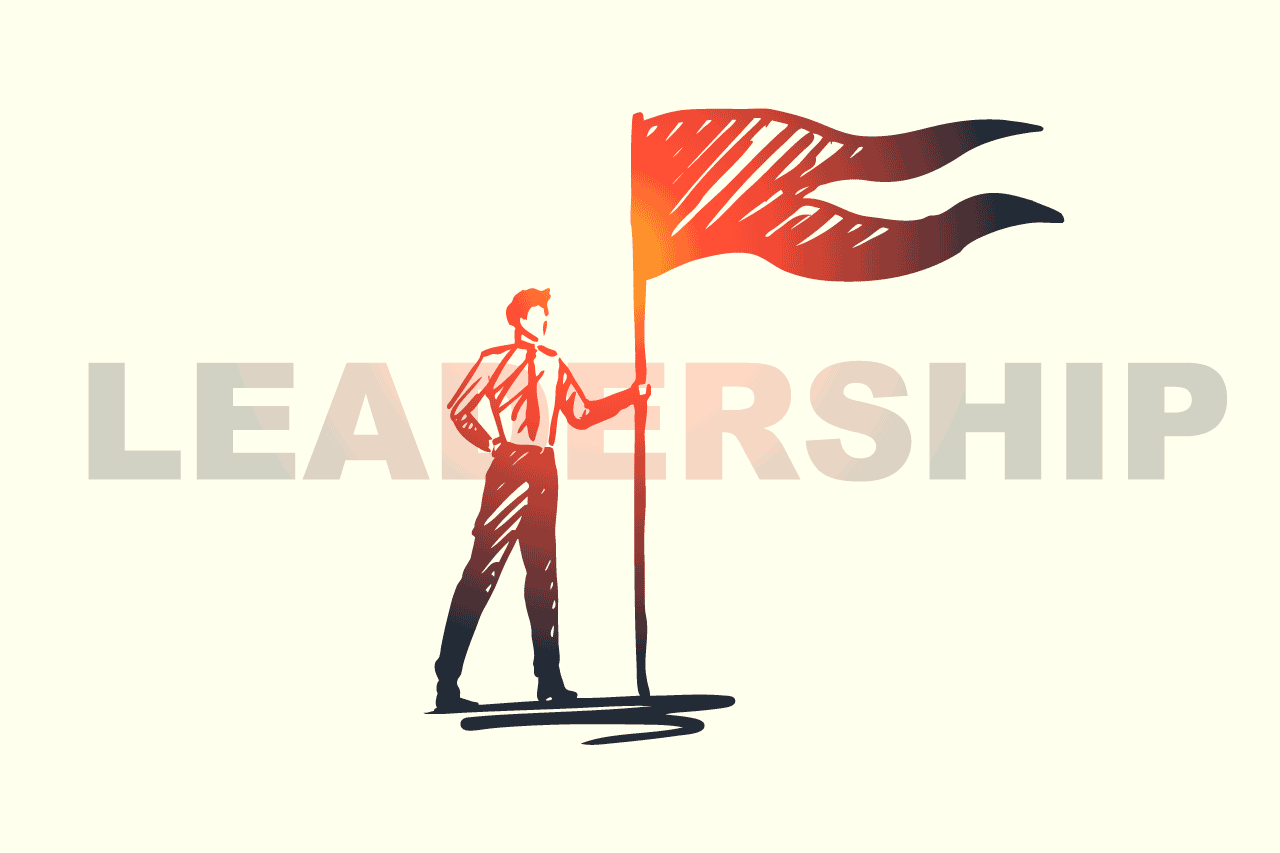
人材育成の4つのポイント。 管理職やマネージャーの、リーダーシップ力向上は必須。
目次[非表示]
人材の育成の4つのポイント
人材の育成には4つのポイントがあると考えます。
新しく管理職やマネージャーというポジションに就く方たちにも同様に、以下の4つのポイントを抑えておいてください。
第一は「チャレンジ」すること
ある程度の基礎力が身についている、もしくは習得できているならば、その現状を超えた、少し背伸びした仕事を与えてチャレンジするチャンスを与えることが成長に繋がると思います。
人は「これはできますか?」と問われれば、自分の能力で確実にできるレベルのものを「できる」と失敗をしないという、守りを固めたような答えをします。それはチャレンジからほど遠い自分の精一杯の力の8割ほどのレベル。
確実に、失敗しない、安全圏の仕事。
このような仕事への取り組みで成長することを期待することがおかしな話です。
チャレンジには失敗はつきものです。
その失敗の中に、成長するチャンスがあると思います。
私がスタッフに伝えていることは、「失敗」を「失敗のまま」にしておくことが一番もったいない。
「失敗」したことの「なぜ」を突き止め、「どうすれば」うまく行くのかを考え、そしてそれを「ノウハウ」に変えることができてこそ、失敗が学びになる、ということを常に伝えています。
第二は「成果」の基準を明確にし、共有すること
「何を」「どのようなレベルにまで」「どうすること」が必要なのか。
第三に、プロセスにおいてもきちんと抑えるべき評価ポイントは何かを共有
成果を評価するならば、たった一つの仕事においてだけではなく、いくつかのプロセスや業務においても評価する必要があると考えます。
そうすることで、そのスタッフの得意なもの不得意なもの。どのようなことによく気がつくか。人との関わり方はどうかなど、自社の社員としての強みを活かすマネジメントを行いやすくなります。
第四としては、コミュニケーションの質と量
コミュニケーションの量と質をあげることで、社内の雰囲気がよくなり、心理的安全性が得られ、そのことによって一人ひとりの仕事の質の向上や生産性の向上が期待できるようになります。

重要度を増している管理職、マネージャーのリーダーシップ力育成。
1970年代にも万事予測不能と言われていた時代がありました。
当時は「乱気流の時代」などと言われていたようです。
現在と状況は違えども、大企業や経団連からも終身雇用を前提にすることが限界になっているなどの発言があり、働き方改革などで今後の環境がどのようになるのかがまだまだ不鮮明だと思います。
ドラッカーが1970年代に行われた取材の中で、「乱気流の時代を生き延びるために必要な4つの心得」として話していることがあります。
- 資源を機会に集中すること
- 資源の生産性を上げること
- 成長をマネジメントすること
- 人の育成に注力すること
まったく今の時代にも当てはまるのではないでしょうか。
人の育成については、重要であることは間違いありませんが、かつてないほど困難な状況だと感じている人事担当者や社長も少なくないのではないでしょうか。
人材育成の研修などは多様なプログラムがいくつも開発されており、新人研修などにもたくさんの時間や予算を費やしている企業もあるでしょう。
しかしながら、人材の定着、戦力化について期待するような効果を得られていないと、問題解決へのアプローチへの悩みはつきません。
企業経営者から「管理職やマネージャーを育成することをまず行わなければ、いくら若手を採用しても育たない」というお悩みを最近よくお聞きします。
全国に多数の支店を持つ企業様のお話では、一つの支店にわずか数人の社員というところもあり、マネージャーの能力次第で売り上げも異なり、マネージャーが転職などで不在になると一気に業績が下降するとのこと。
管理職やマネージャーへの期待として、これからを見通し、計画し、組織し、資源を適切に配賦し、目標設定を行い、成果を評価し、リーダーシップを発揮し、マネジメントし、人を育成し、適切な配置や役割を提示し、やる気を起こさせるなど、気が遠くなるほどの責任と役割を組織が管理職やマネージャーへ依存しています。
成果をあげるためのポイントは強みを活かすこと。

成果をあげるためには社員の強みをコミュニケーションによって発見し、既存のルールのなかでは発揮できなかったような潜在的な能力を活かすことです。常に社員の得意とすることにフォーカスし、リーダーシップを発揮できる環境やチャンスを提供することで、一人ひとりの成長を促していくことだと感じます。
もう一つ、成果をあげるための人材の活かし方について、ある方の話の中でなるほどと思ったことを書いておきます。
話していたテーマは優秀な人材に何を担当させるかということです。
- 成果をあげることを担当させる
- 挑戦的なこと、難しいことを担当させる
当たり前のようでいて、多くの組織が優秀な人ほど、厄介ごとを担当させていることが問題だということです。
優秀な人材は問題解決の能力も高く、ついそうなってしまうのも理解はできますが、自分自身もよく反省し、これからの人事において心がけたいと考えています。
おすすめ関連記事