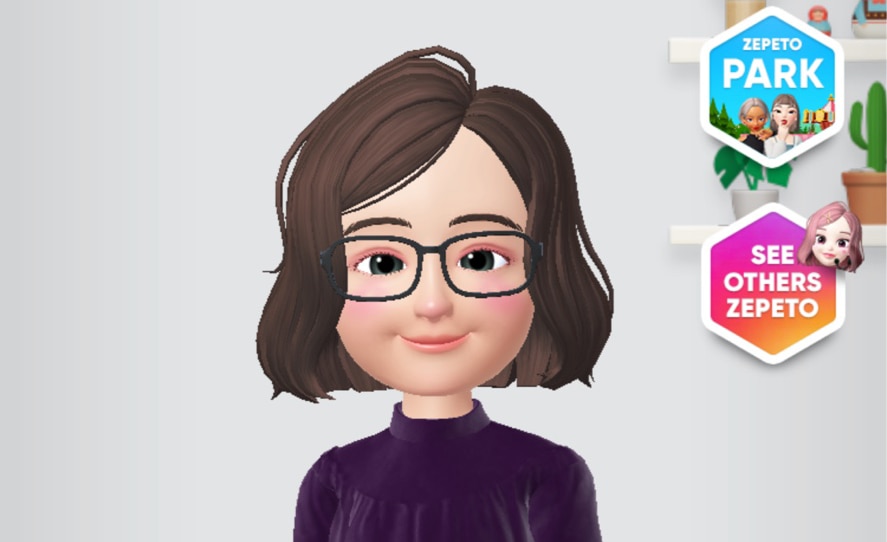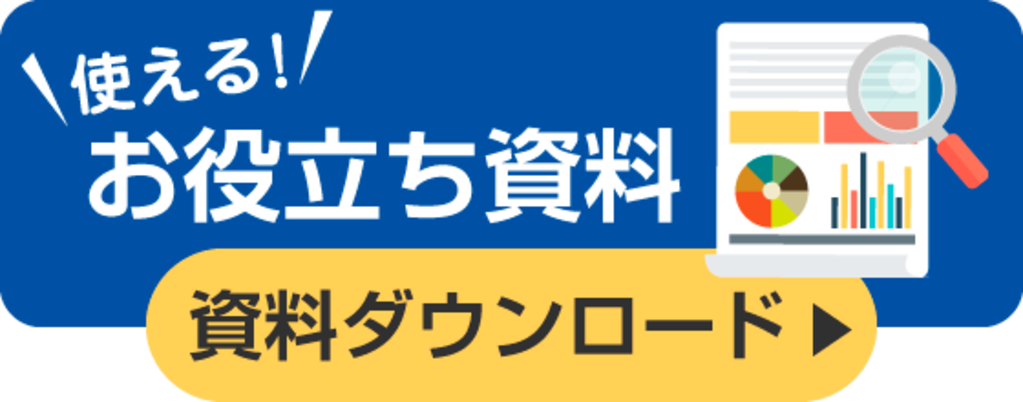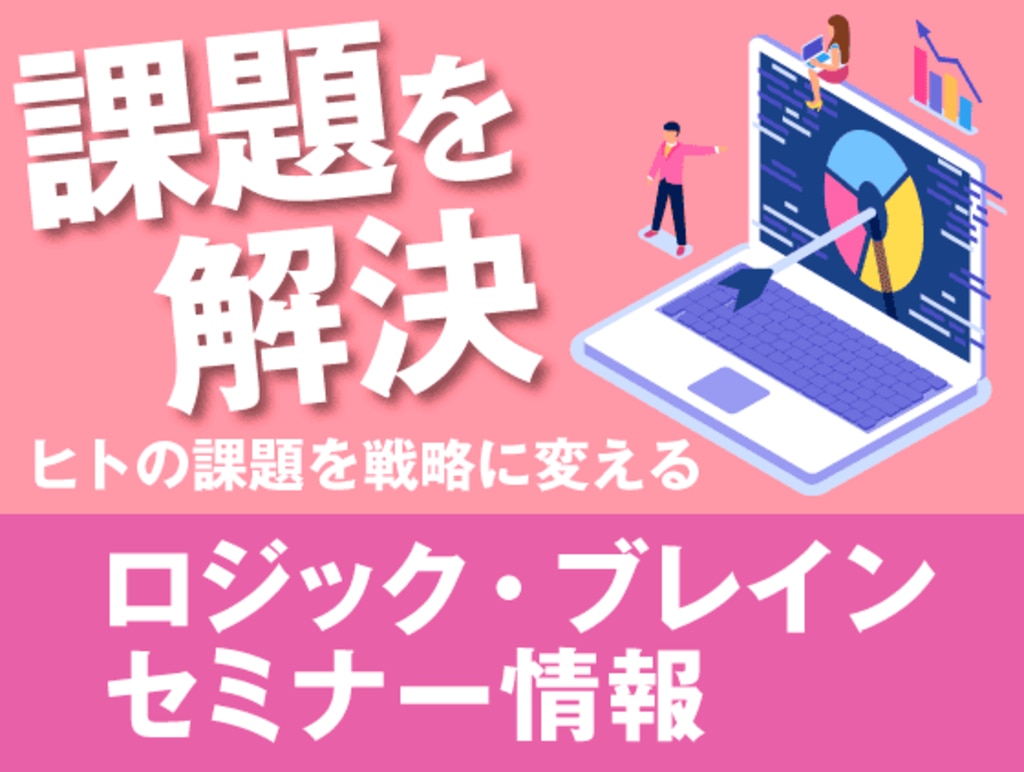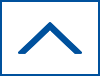2020年、組織活性化のための5つの要素
2020年代に起きる変化とは?
新年あけましておめでとうございます。
お正月休みはいかがお過ごしでしたでしょうか?
新年最初のブログのテーマを何にするかを悩んでおりましたが、やはり干支にちなんだお話から始めてみようと思います。
2020年の干支はご存知の通り「子年」
子年は今までの事は一旦終了させて、一から始める「了と一」年と言われています。
今年はオリンピックイヤーでもあり、2025年の大阪万博までの間に、様々な世界のテクノロジーやサービスなどが世の中に紹介されていくスタートの年となります。
今まで想像もしていなかった新しいものが当たり前になる時代。
今まで当たり前だと考えていたことが、廃れていく時代。
または、今まで廃れていたものが、テクノロジーを使って新たなサービスとして活用される時代。
例えば過去を振り返ってみて、今はSNSの活用が多くなってきているとはいえ、BtoBの間ではメールの活用率は高くとどまっています。
昔の手紙文化は一旦廃れてしまいましたが、メールという新たなサービスによって人は一日に何通もの手紙(メール)を書いています。
そしてBtoCにおいてはSNSなどの活用も頻繁に行われています。
手紙の文化を俯瞰でみれば、一周ぐるりとまわって手紙文化の再来といえますが、ヨコから見れば、テクノロジーを活用してらせん状に成長しているのです。
この後の皆様の周りに起きる変化はどのようなものなのか?
これまでに見たことのない、体験したことのない新しいサービスやコンテンツ、テクノロジーかもしれません。
もし、そうであるならば、今までの流れに沿ったものではなく、まったく新しいスタートを切るべき時かもしれません。
今までの流れや常識を一旦完結させて、新たにイチから始める。
従来の価値観に縛られていたのでは、今から起こる新たな未来へのチャレンジのタイミングも逃してしまうことになり得ます。
これからのマネジメントに必要なこととは。
企業を取り巻く経済環境や、対応していかなくてはならないルール、新たなサービスや技術革新。
ビジネスサイクルが急速に短いスパンとなり、マーケティングでも半年経てば、すでに新たな取り組みが紹介されています。
中小企業や個人事業主といえども、この波に影響されないままではいられません。
技術や知識の更新スピードが高まり、企業が蓄積してきたノウハウ、知識の陳腐化が早まり、組織が生き残っていくためには、新たな知識の習得、設備の投資など積極的に取り組む必要があります。
世界のトヨタでさえ例外ではありません。エンジン車の特許はこれ以降、今までのような価値を企業にもたらしません。
まだこんなにもビジネスサイクルが短縮化されていなかった時代は「ヒト」「モノ」「カネ」が企業がビジネスを行う上で重要な資源だといわれてきましたが、今は「モノ」「カネ」から「知識」へと以降され、「知識の時代」「知識経済の時代」と言われています。
資金や資本を保有していることが重要視されてきた株式公開においても変化が見られています。
最近では「赤字上場」が急増しているのも、時代の流れと言えます。
ITベンチャーが増えているため、先行投資がかさんで赤字上場となっても、投資家が成長に期待して許容しているということです。
どのような知識やノウハウを持っているのか、そしてそれを常に更新し、環境変化に適用させているのかが重要となっています。
こうした時代背景から、従来のようなトップダウンで行っていたマネジメントで見られていた「統一性」「効率性」「均一性」「秩序化」という統制型の組織では時代の早すぎる流れには対応しづらくなっています。
それぞれの組織やそこに所属するメンバーが自律型で変化に対応した価値を創造していける、そんな「学習する組織」が求められています。
「学習する組織」に必要とされる概念とは。

MIT(マサチューセッツ工科大学)のピーター・ゼンゲ氏が1990年に著した『最強組織の法則』で、30年も前に、すでに書かれていた5つの構成要素について紹介します。
【自己マスタリー】
「自己マスタリー」とは、自分自身の目標と現状のギャップを課題と認識し、常にこうありたいと願う自分自身の未来に対して積極的に学ぶ姿勢や原動力ということ。
【メンタルモデル】
「メンタルモデル」とは個人が持つ「思い込み」や「固定観念」を指し、常にブラッシュアップさせることで組織の活性化を促し、改善や自己啓発を続けること。
【共有ビジョン】
「共有ビジョン」とは組織全体が共通の未来像や目標を持ち、それに向けて自己啓発をすすめる組織環境を作り出そうとすること。
【チーム学習】
「チーム学習」とはチームメンバーの間で本当に得たい成果について、メンバー間の対話を通して学習を引き出し、個人力の総和を越えたチームの能力を創造すること。
【システムシンキング】
「システムシンキング」とは、複雑に関連しあっている問題の全体状況と相互関係を明らかにすることで解決策を見いだす技法のこと。
5つの構成要素はまさしく、企業の【ミッション】【ビジョン】【バリュー】についてチームと話しあうこと、何でも話し合えるという「心理的安全性」を担保することなど組織風土を整えることだといえます。
自分たちの存在意義をチーム全体で共有し、それらを示すために「何故それを行なうのか」「どのように行うのか」がチームの原動力となる時代。
学習する組織とはコミュニケーションによって信頼し合える仲間と【ミッション】【ビジョン】【バリュー】について自分たちの行うべき行動を共感、共有できている組織と言えます。
(学習する組織、5つの構成要素 参考資料:https://www.humanvalue.co.jp/wwd/research/insights/articles/post_5/)
個性、性格を研究してきたロジックブレインだから、パーソナルのインサイトが可視化された情報を提供することができます。
ビジネスの進め方、価値観、マネジメントから個人の能力など、インサイトが一目瞭然のメソッドだから、一人ひとりの仕事の進め方も一目瞭然。
ロジック・ブレインの組織分析でチームの課題や特徴が明確になり、パーソナルの能力を活かした組織、チームの活性化に役立ちます。