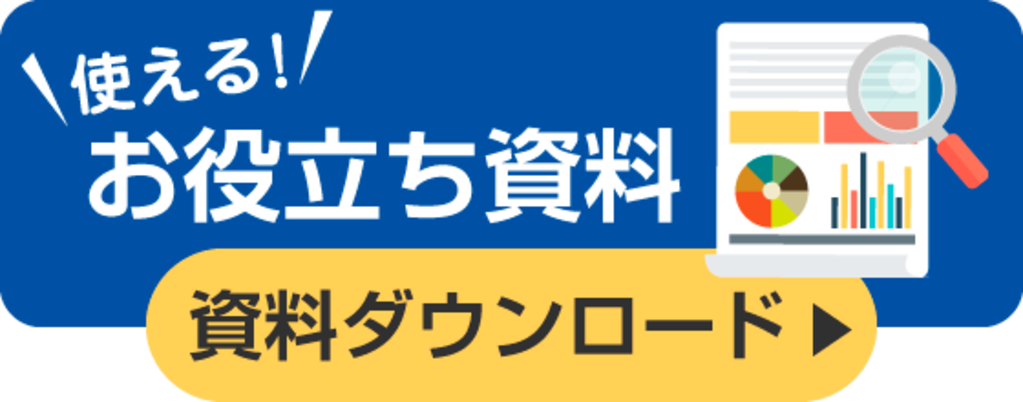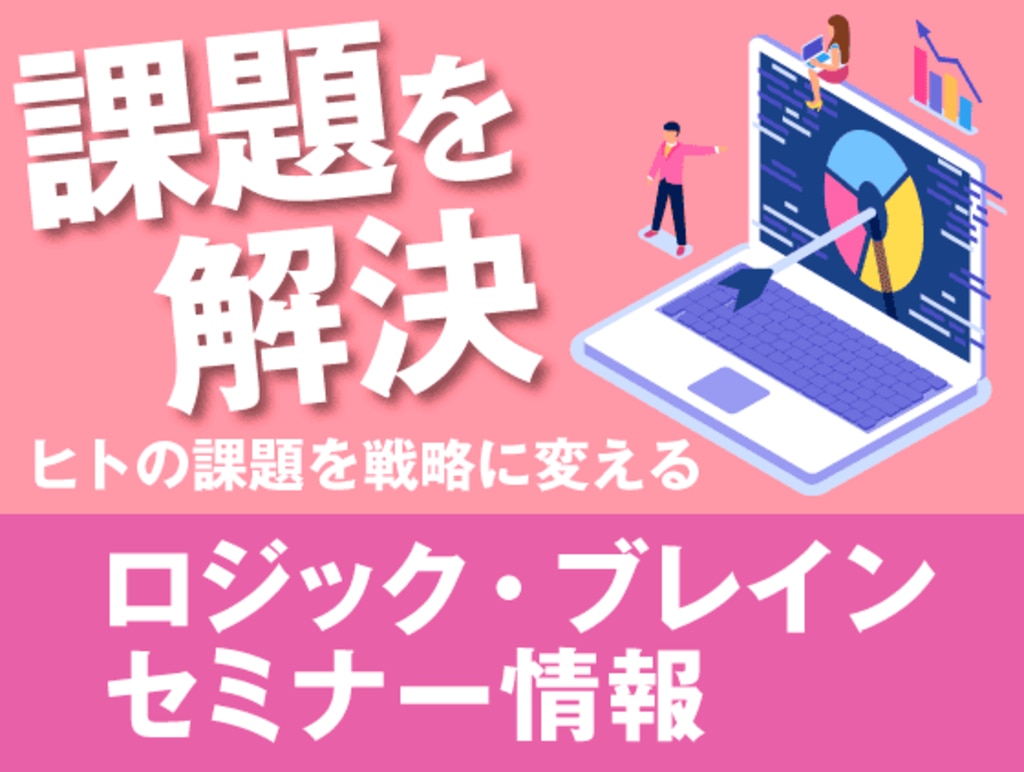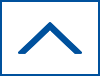自社にピッタリの人材を見極めるメソッド--我が社の事例
人材採用-成長企業に見られる苦難の歴史
人事や面接担当者は、自社にピッタリの人材を見極めることを真剣に考えていますし、入社してもらったならば、優秀な人材として長く勤めてもらいたいと考えています。
私も今では、リーダーやマネージャーたちが面接した人材の最終面接を行うだけになりましたが、設立当初から12、3年間くらいはリクルーティングの広告媒体や人材紹介会社との折衝、面接などすべて一人で行っていました。
現場の仕事もしていましたし、このままではどの業務もまわらないくらいの状況でした。
特に私が大阪をベースにもう一つ東京にオフィスを構えようと動き出したのが平成16年。
今から15年前になります。
東京にオフィスを出したからといって上手く行く保証は何もありませんでしたが、運良く大阪の印刷業や広告代理店なども仕事を求めて東京への出店ラッシュのタイミングでした。
当初クライアントもなく東京に来たというのに、仕事のオファーが人の採用が間に合わないくらいになり、酷い時には派遣社員に派遣社員を指導させるというギリギリの状態だったこともあります。
採用といっても誰でもいいわけではありませんでしたが、真剣に面接をして見極めようと最大限努力しても、今日の人手に困り果てていた私は、とにかく業務内容をイチから説明しなくても、仕事をこなしてくれる人を採用したという時代でした。
これまでに何度も「失敗したな…」という苦い経験。
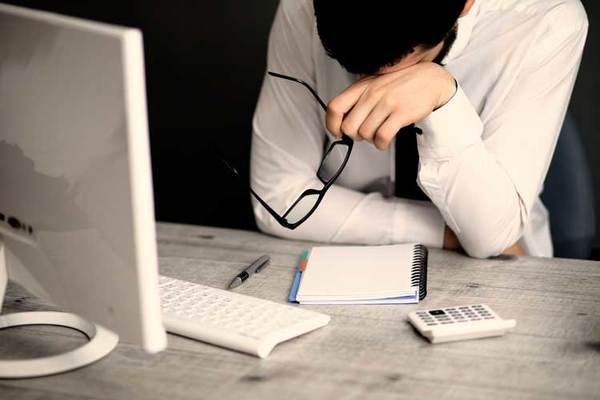
先ほどの東京進出時代というのは、会社が急成長していたので、人手が全く足らないわけです。
今ではそこまでのことはありませんが、私がまだ現場で頑張っていたころは徹夜や深夜までの仕事は日常的で、さらにありとあらゆる仕事を、私が関わらないとやっていけないという状況でしたから、正直、もう自分の体がもたないと感じていました。
その頃はまだ今と違って求人広告を出せば、人材が集まる時代でしたので、
次から次にどんどん採用しました。
その時代は、採用のペースよりオファーの数が上回る状況でしたので、頭数を揃えるのを優先していました。もちろん選考はしていました。ですが、現場が疲弊するほど人が不足していたのです。
ちょっと良い学校を出ている人、ちょっと良い会社で経験がある人。
もう、そういう人はほとんど無条件で採用していたと思います。
ところが、これが負のスパイラルの始まりでした。
現場は若い人材が多かったので、私が良いなと思うキャリアを積んできた人や、自走力がある人など、能力が高い人を集めようとしていました。しかし、そのような優秀な人材はいくつもの企業からも内定をもらっているなど、引く手あまたなので、ほとんど採用に至らず、なんとか入ってもらえても思ったような活躍をしてくれないというのが続きました。
急場しのぎの採用が続いていいたこともあって、私と価値観が合わない人も少なからずいました。
私が指示してもすぐに動かない。
仕事の進め方を理解してくれない。
他のメンバーと反りが合わない…。
結果、彼らの「仲」を取り持つことや、彼らを「教育」するために、自分の気力と時間をとことん使うことが増え、それまで以上に身体にも心にも負担が重くなってしまったのです。
そのころは入社の人数も大かったけれど、退職する人数も多く、「何のために採用したのか…」と徒労感でいっぱいでした。
『人材採用術を極めたい』人事担当者必読。
一般的な採用は、スキルや学歴、面接で話した時の印象・・・
こういったことを面接する担当者は何となくの感覚で採用しています。
それはそれで、大切なことです。
いくつかの要素をしっかりと見極めることで失敗しない採用を行えるのです。
【1つ目の確認ポイントは人間性】
「人間性」とは人間として生まれつき備えている性質を意味しています。
思いやりの心、気遣いの心、愛情など、人間の内面のことを指し、
類語として「人徳」「人間力」「人格」「人柄」など、が挙げられます。
「人間性」の高い人は、人の気持ちを考えて行動することができます。 相手を思いやることができるのは人間らしい性質です。そのため人間性が高い人は周囲のことをよく見ることができるだけでなく、気遣いができます。
【2つ目の確認ポイントはビジネスの進め方】
ある意味、仕事を進行していく上での価値観とも言えます。
典型的な例でいうと、「仕事はスピードだ!」という上司がいます。
ところが反対に、「仕事はスピードより、丁寧さが大事」という部下がいるとします。
もし上司が、スピードを優先して物事を考えていく、仕事を進めていくという人だとしたら、スピードより丁寧さを優先している部下のやり方は上司とは合わないということになります。仕事をしていてもお互いの価値観が合わないので、上司は不可のことを扱いづらいと感じるでしょう。当然高い評価は得られないことも。
上司と部下が逆のパターンであっても同様です。
上司にはこのような価値観を持った部下もいるという「相手理解」を指導する必要があります。そして自分の価値観は何なのかという「自分理解」を既存の従業員たちに指導することも同様に大切なことです。
「自分理解」「相手理解」ができる組織は心理的安全性が高い組織と言えます。
【3つ目の確認ポイントはカルチャーフィットが可能かどうか】
入社してから半年ほど経つと、入社の頃の印象とは違うということを感じることはありませんか?
面接時には「見せる自分」で対応していますから、個人の本質は何かを知る必要があります。
これは長年の感や質問力でカバーしている熟練した人事担当者もいらっしゃいますが、中小企業などで人事部を設置できる企業はどれほどあるでしょうか?
にわか人事となった担当者の方でも、応募者のインサイトがわかると失敗しない採用が行えるのです。
将来的にこのチーム、組織にフィットする人材を獲得することが、求められています。
人事担当者必読の3つのポイントについて個性、性格を研究してきたロジックブレインだから、
わかりやすく可視化された情報を提供することができます。
ビジネスの進め方、価値観、マネジメントから個人の能力など、
一目瞭然のメソッドを体感しませんか。
詳しくは下記資料ダウンロードのボタンを押してください。