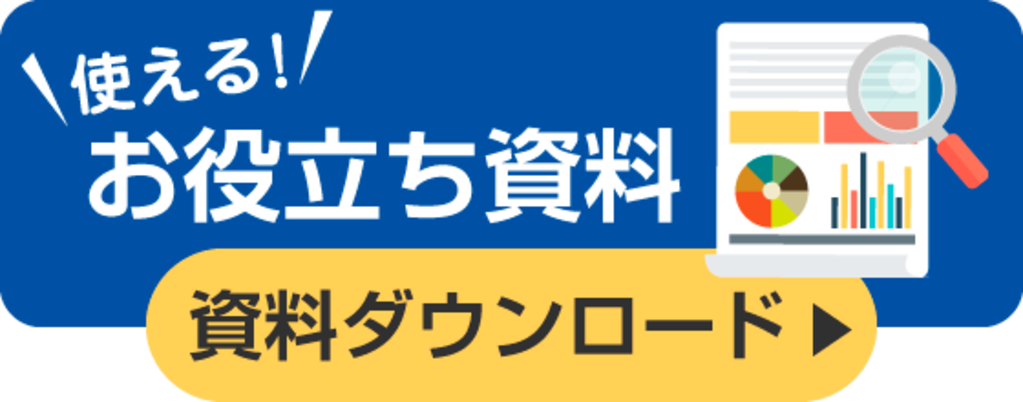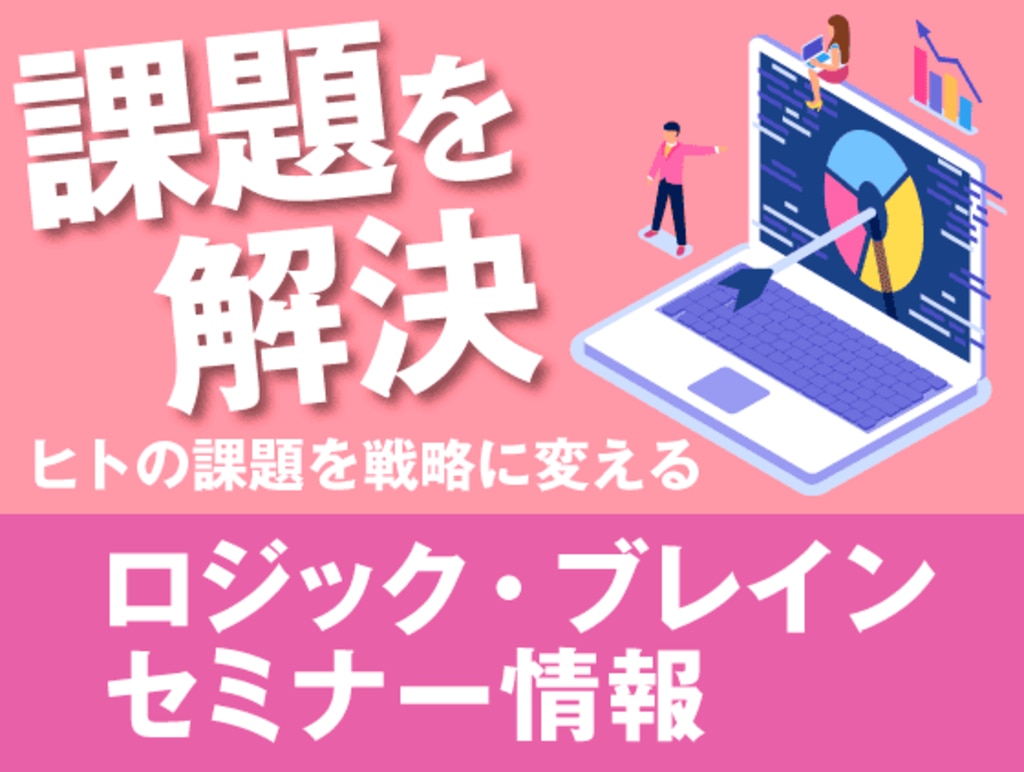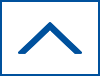企業のエンゲージメント対策に大切なこと
目次[非表示]
従業員エンゲージメントとエンゲージメントドライバー
最近少しずつ認知されてきた「エンゲージメント」という言葉。
従業員のエンゲージメントについてどのような取り組みをすれば良いのか、考えたことのない経営者はいないと思います。
一般的に従業員のエンゲージメントとは、
従業員と会社がお互いに貢献し成長できる関係になっているかということを意味し、従業員が会社や職場に対して愛着や信頼の度合いをアンケートや意識調査などにより可視化・数値化して把握します。
従業員エンゲージメントが高いほど、離職率が低いだけでなく売上高が向上し、営業利益率が高いなど企業の生産性に貢献しているという結果がでています。
では、どのような方法でエンゲージメントを高めれば良いのでしょうか。
エンゲージメントを高める要因(エンゲージメントドライバー)としては、
- 企業のミッション・ビジョン
- 社会的意義
- 上司や同僚との人間関係
- 仕事の業務量
- 勤務条件
- 福利厚生
- 公平な評価制度
などが挙げられます。
本来従業員エンゲージメントの把握には、アンケート形式の意識調査を用いて数値化、もしくは何らかのカタチで可視化します。
しかし従業員との対話や意識調査などの方法などに慣れていない場合、たとえば匿名アンケートの場合でも、回答内容が会社に伝わるという懸念から従業員が本音を回答せず、実態を把握することができないといったことも考えられます。
このように考えると、従業員エンゲージメントに取り組むにはまだまだ道のりが遠いと感じる方もいるかもしれませんが、ここにあるような可視化、数値化することは後でも良いのです。
まずは対話から始めてみることで良いのです。
「対話」には、「1on1ミーティング」を始めてみましょう。

「1on1ミーティング」といってもいったいどんな内容を話せば良いのかというのが、初めての「1on1ミーティング」で上司の方が悩むポイントです。
会社のミーティングといえばこれまでは上司・部下の間で対面でのコミュニケーションでは目標管理や成果などについて人事考課的な半年に1回の面談が主流でした。他の場面で1対1面談となると、上司からネガティブな指摘事項が思い浮かび、部下としては「面談」はポジティブな印象を持っていないかもしれません。
これまで上司と部下の対話においては「上司が一方的に指示・指摘する」ことが多く、面談とはそういうものだという習慣が新しい取り組みを難しいと思わせている原因といえるでしょう。
「1on1ミーティング」の目的は、部下や従業員の成長を促進することが目的ですから、「管理のための時間」ではないことを上司はしっかりと意識しておくことが大切です。
ついうっかりといつもの人事考課や業務ミーティング時の面談のように話してしまうと、従業員からすれば「対話」ではなく「指示・指摘・伝達」になってしまいます。
従業員の方もいったい何を話せば良いのか最初は戸惑ってしまうかもしれません。
私の経験からも、最初は従業員からの話題、テーマなどはほとんど出てきませんでした。
ですが、この機会にエンゲージメントドライバーとして挙げた企業のミッション・ビジョン、社会的意義、これから取り組むことの重要性などを従業員一人一人にしっかりと伝え、皆の思いや考え方、意見を聞こうと考えました。
これからも回を重ねる毎に、上司や同僚との人間関係、仕事の業務量、勤務条件、福利厚生、公平な評価制度など、これらひとつひとつについて、丁寧に聞いていこうと考えています。
エンゲージメントドライバーを従業員と一緒に考えてみるとどうなる?
経営者や管理職の方々は従業員のエンゲージメントを高めるために、従業員たちのやりがいや成長意欲を満たす環境を作ることを常に考えています。
それらを整えることによって離職率を抑え、業務の生産性を高め、自らの考えで責任をもって行動することのできる人材の育成を行いたいと考えています。
環境というと、ハード的なことを整えることと勘違いしがちですが、リーダー(経営者や管理職の方々)が最初に行う事は『ルールを決める』ということです。
- 時間や期限を守る
- 必ず自らの意見を述べる
- 上司は部下の意見やアイデアを頭ごなしに否定しない、または答えとして指示を出さない。
- 上司は部下の意見などを傾聴する。
- 定期的なコミュニケーションを取るための時間をつくる
など、従業員たちが積極的に参加できる仕組み(環境)をつくることから始めてみると良いでしょう。

そして企業のミッション・ビジョン、社会的意義、上司や同僚との人間関係、仕事の業務量、勤務条件、福利厚生、公平な評価制度、などをについて対話し、一緒に考え、創りあげていく過程で、従業員たちの発言や行動が変化していくのがわかります。
この過程で次によくある質問が、「従業員たちから出てきた意見はどこまで受け入れれば良いのか」ということです。
従業員たちの意見を聞くことは大切ですが、望むとおりのことをすべて叶えるということとは違います。
自主性を重んじることと、何でも自由にさせることとは違いますから、きちんと話し合うことが大切です。
インターナルブランディングを従業員と一緒に造りあげていくことで、従業員の成長も促せ、結果としてエンゲージメントを高めることができるのです。